
JR西日本は2024年5月18日、株主照会通知にて2025年以降に在来線車両を173両投入すると公表した。今回はこのうち岡山県内の車両置き換えについて見ていく。
1. 新型車両227系だけでは足りない岡山県内の普通電車置き換え!
JR西日本では2023年7月22日より岡山県内に227系を導入することで車両更新を図っている。
227系は近畿地方と中国地方のJR西日本管内の従来の4両編成以下の直流電車の置き換え用として導入している2両または3両編成の車両で、227系置き換えによりその線区のすべての普通電車を置き換えることを原則としている。
広島支社向けには新型車両227系は2015年より276両を投入し、管内の115系4両編成47本、113系4両編成14本、105系2両編成14本、103系3両編成3本の計281両を全て置き換えた。281両を276両で置き換えたのは多少の減車はあるものの可能な範疇ではあるし、2022年3月12日JR西日本ダイヤ化改正での減便でさらに115系4両編成2本を運用離脱させたことを考えると289両を276両で置き換えたと言ってもいいだろう。ただそれでも車両数は4.4%減にとどまっている。
113系の52両、115系の157両、117系の24両の合計233両を101両で置き換えるのは56.7%も減少しており、到底不可能である。
また新型車両227系500番台に車番226-592が登場したというが、おそらく92編成まで投入しようではなく線路モニタリング装置などの特殊装置を設置した車両になりそうだ。
一方で、JR西日本ではAシートを設けた新快速用225系4両編成を増備する見込みがあり、余剰となった車両を奈良線へ転属、奈良線の205系4両編成9本が余るわけだが、これで岡山に転入しようものなら、岡山県内に103系を投入したとき並みの悪夢である。
そうなると考えうるのは、瀬戸大橋線快速マリンライナーに新型車両を導入、223系やJR四国5000系の普通車自由席を普通列車に転用すればある程度まかなえるのではないだろうか。実際JR西日本では過去に初代瀬戸大橋線快速マリンライナー用車両213系を普通列車用に転用したことがある。2代目快速マリンライナー223系+5000系も2003年の走行開始から20年が経過しているんだ、車両更新工事に合わせて普通列車転用をしてもおかしくはない。
岡山県内への227系導入数が少ないにもかかわらずJR西日本の車両製造数が多いのは瀬戸大橋線快速マリンライナーに新型車両を投入し223系およびJR四国5000系をJR西日本岡山支社管内普通列車に置き換えるのではないだろうか。
2. 瀬戸大橋線快速マリンライナーの車両置き換えへ!
では瀬戸大橋線快速マリンライナーにどのような新型車両を導入するのだろうか。
そもそも瀬戸大橋線快速マリンライナーは1988年4月10日の瀬戸大橋開通に合わせて運行を開始した岡山と高松を結ぶ列車であったが、当初は全車JR西日本213系による運転で高松方1号車が展望グリーン車、2号車が普通車指定席、3号車~6号車(一部9号車)までの基本4両の自由席を連結していた。
が両数が多いと固定資産税がかかることもあり、車両性能向上による最高速度130km/hへの引き上げを図り岡山~高松間の所要時間を短縮するべく2003年10月1日にJR四国5000系3両+JR西日本223系2両に車両更新、展望グリーン車と普通車指定席を1号車に集約し1号車2階をグリーン車、1号車1階を普通車指定席とし1両減車した。
ただ1号車を2階建てとしたことで階段昇降が必要となりバリアフリーから遠くなってしまった。また多目的トイレも設置していない。高松からの山陽新幹線連絡列車としては機能が不十分なのである。
しかも2階建て車両が先頭車ゆえ空気抵抗も大きいし、グリーン車や普通車指定席を利用する人自体も減っている。近年の特急列車の車両更新ではグリーン車が1両の場合多目的トイレをグリーン車両に設置することでグリーン車から座席数を優先的に減らしたり、グリーン車を1両から半室に減らしたりグリーン車の連結自体を取りやめる列車まで出てきている。
実際岡山周辺では伯備線特急「やくも」も2024年4月~8月の381系から新型車両273系への置き換え時にグリーン車を1両から半室に削減しているほか、瀬戸大橋線を通る予讃線特急「しおかぜ」や土讃線特急「南風」のグリーン車は0.5両分しかない(なんなら2000系時代は特急「南風」の一部はグリーン車を設置していなかった)。いや、予讃線特急「しおかぜ」のうち旧来型車両の8000系と特急「南風」の旧型車両2000系はグリーン車が18席あったのに、新型車両である8600系と2700系は12席に減っているのである。半室とはいえグリーン車の座席数を減らし、その分普通車指定席を増やしているのだ。
岡山と高松の間の都市間輸送の役割も持つ瀬戸大橋線快速マリンライナーも同様で、2003年10月1日より運転を開始したJR四国5000系の1号車はグリーン車36席、普通車指定席34席となっている。高松方面は利用が多いと言えど特急「しおかぜ」の2倍の30分間隔で来るので1列車あたりの座席数はそこまで必要ない。
そこで瀬戸大橋線快速マリンライナーの車両更新を図り1号車を半室グリーン車と半室普通車指定席の平屋構造とすることでバリアフリー対応とするほか、空気抵抗を減らし、運行費削減を図りに行くのではないだろうか。
3. 快速マリンライナーグリーン車グレードアップで値上げへ!
JR西日本とJR四国が運行する瀬戸大橋線快速マリンライナーであるが、快速マリンライナーのグリーン車はまさかの2人掛け&2人掛けとJR東日本の普通列車グリーン車並みの窮屈さを誇っているのである。
これは5000系1号車がJR東日本E231系の2階建てグリーン車の技術供与で製造したものであるからなのだが、JR東日本の普通列車グリーン車と異なり快速マリンライナーは岡山と高松を結ぶ都市間列車でグリーン車利用ともなれば特急列車のグリーン車と同等に利用したい人たちなんだは。しかも岡山~高松間のグリーン車連結列車は快速マリンライナーしかないので在来線なのに2人掛け&2人掛けの窮屈なグリーン車利用を強いらざるを得ない。
これを解決するには快速マリンライナーのグリーン車は特急列車のグリーン車と同等の設備を持つことである。
東京近郊の在来線特急列車を除き在来線特急列車のグリーン車は2人掛け&1人掛けとなっている。新幹線では2人掛け&2人掛けが標準だが、これは車体幅が広いため1人分横に増やせることによる。
つまり居住性の向上を図る目的で新車更新の際に快速マリンライナーのグリーン車を2人掛け&2人掛けから2人掛け&1人掛けに変更する可能性が高い。

381系特急やくものグリーン車内。2人掛け&1人掛けでゆったりと過ごせる。快速マリンライナーも高松と山陽新幹線の通る岡山をを結ぶ列車なのだから、グリーン車くらいは特急と同レベルが必要だろう。
では瀬戸大橋線快速マリンライナーのグリーン料金はどうなるのだろうか。JR西日本では2020年からの大幅な旅客減少により収入を補うため、2022年からの順次在来線特急列車全車指定席化、2023年4月1日料金改定割安なB特急料金の廃止や山陽新幹線「のぞみ」「みずほ」の値上げ、大阪近郊でも特定区間運賃の値上げなどで増収を図っている。このため瀬戸大橋線快速マリンライナー車両更新時に運賃のほか料金を徴収しているグリーン車と普通車指定席でも値上げを目論んでいるだろう。
現状グリーン料金は50kmまで通年780円、100kmまで1,000円であることからもし普通車指定席が840円に値上げするとなればグリーン車の方が安くなってしまいかねない。このためグリーン車の値上げも当然行うだろう。
またグリーン車利用客は在来線特急列車相当のグリーン車を求めており、車両更新で座席も2人掛け&1人掛けにするとなると特急料金相当額を徴収してもよいはずだ。JR四国の立席特急料金は50kmまで760円、100kmまで1,200円であることから、それぞれの立席特急料金相当額をグリーン料金に加算した場合快速マリンライナーのグリーン料金は50kmまで1,540円、100kmまで2,200円と2倍程度に値上げとなる。
まあ正直快速マリンライナーでグリーン車に乗るような人は支払い能力が極めて高い裕福な人なので設備さえこしらえておけば支払ってくれるだろうから2倍に値上げしても問題はないし、2023年5月20日JR四国運賃料金改定で新幹線と特急列車の乗継割引が廃止となった際に新幹線~岡山経由~松山・高知間で自由席からグリーン車まですべての座席で約2,000円値上げしていることを考えると、110円しか値上げしていない新幹線~岡山~高松間の運賃からグリーン車だけ1,200円値上げしても結果1,310円しか値上げしていないので松山や高知と比べればそれでも良心的だろう。
4. 普通車指定席も座席グレードアップで840円に値上げへ!
また瀬戸大橋線快速マリンライナーの指定席も特急列車と同等の座席とすることで座席指定料金の値上げを図ることができる。
1988年の瀬戸大橋開通に伴う快速マリンライナー登場時は快速列車の座席指定料金は300円~500円が主流で、今でも快速マリンライナーの普通車指定席は運賃に330円~530円加算すれば乗車できる。が、2019年よりJR西日本では新快速に特急普通車座席と同等のAシートを導入、座席指定料金を通年840円とした。この座席指定料金通年840円は徐々に広がりを見せつつあり、JR北海道では2022年3月12日より千歳線快速エアポートのuシート指定席を840円に値上げ、2024年8月1日から北海道内の普通列車の指定席は原則840円となる。
ただJR西日本ではそのあとに指定席を設定した場合でも大和路線区間快速うれシートなど座席が自由席と変わらない列車の指定席は従来通り330円~530円としている。つまり値上げをするのであれば指定席座席のグレードアップが必要という認識のようだ。そこで快速マリンライナーでも新車更新に際し普通車指定席を特急列車仕様とするのではないだろうか?
もし瀬戸大橋線快速マリンライナーの指定席を特急列車と同等のものにすれば伯備線特急「やくも」用273系普通車指定席と部品を共通化できるので保守メンテナンス費用を抑えることができる。合理化もできるし値上げもできる、JR西日本からしたら一石二鳥なのだ。
そもそも瀬戸大橋線快速マリンライナーの走る岡山~高松間は運賃1,660円、岡山~坂出間でも1,210円もする。これは瀬戸大橋線加算運賃や2度にわたるJR四国単独の値上げがからんでいるのだが、所要時間約55分と40分であることを考えると所要時間のわりに割高である(もっとも130km/h運転を行っているから速いというのもあるが)。普通車自由席のみの利用でもこの運賃はかかる。
ただJRの運賃制度の関係で新幹線と通しで300kmを超える場合乗車券を購入すると遠距離低減措置により1km当たりの運賃が安くなる。実際東京~岡山間の片道乗車券は10,670円、東京~高松間の乗車券は11,850円なので差額980円で快速マリンライナーの普通車自由席を利用することができる。しかも往復割引1割引を効かせようものなら岡山~高松間は差額880円相当で利用できてしまう。もし指定席に乗っても最大530円しか加算しないので岡山~高松間自由席利用1,660円よりも安く利用できる。おいおい、乗車券が遠距離で安くなるのはそうだとしても新幹線からの乗継利用者が多い指定席やグリーン車を利用する際にはもっと値段を上げるべきだろう。
普通車指定席は新快速Aシートのような特急普通車座席仕様の座席にすれば座席指定料金330円~530円を840円に値上げ可能だ。これにより岡山~高松間で普通車指定席を利用する場合は1,990円~2,190円から2,500円に値上げするし、新幹線からの乗継利用に際しても310円~510円の値上げとなり増収を図ることができる。
もし瀬戸大橋線快速マリンライナーの1号車を平屋とし、座席配置をJR四国8600系(「しおかぜ」型車両)と同等にするのであれば、1号車はグリーン車12席と普通車指定席17席を用意することになりそうだ。現在の約半分に減るがそれでも十分座れるだろう。
別に座席指定料金を払いたくなければ2号車~5号車の普通車自由席を利用すればよい。自由席でもクロスシート車なので比較的快適だし昼間はたいてい座れるので。
5. マリンライナー自由席は4両のまま存置か
ここまで瀬戸大橋線快速マリンライナーの新車置き換えに際し1号車のグリーン車と普通車指定席は平屋化によるバリアフリー化と空気抵抗削減により維持費用削減に努めることができるほか、座席グレードを上げることで特急列車並みの料金設定に値上げし収支改善できることが分かった。
ではさらなる合理化を目的に自由席の減車はできるのだろうか。
瀬戸大橋線の2018年度の輸送密度は岡山~茶屋町間が42,374人/日・往復、茶屋町~児島間が29,026人/日・往復、児島~宇多津・坂出間が21,407人/日・往復となっている。このうち特急列車利用者が8,009人/日・往復いるほか、岡山~茶屋町間は普通列車利用者も多いので必ずしも全員が快速マリンライナーを使うとは限らない。
茶屋町~児島~坂出間は特急を使わないほとんどの乗客が快速マリンライナーを利用することになる。普通列車の自由席で昼間毎時1両で4,000人/日・往復運びきれるとすると、特急分を除いて毎時6両あれば運びきれる。快速マリンライナーは毎時2本(30分間隔)の運転があるから、昼間は1列車あたり3両の自由席があれば十分着席できる。
一方で平日夕方は茶屋町~児島間で毎時8両が必要なことから快速マリンライナー1列車あたり4両の自由席が必要になるし、平日朝は茶屋町~児島間で毎時12両が必要なことから快速マリンライナー1列車たりの自由席は6両必要となる。平日朝は特に茶屋町→岡山間で混むことから普通電車と合わせて10分間隔で運転するほどだ。
まあ近年地方路線では旅客量が減っているので隙あらば減車減便を行っているのだが、瀬戸大橋線沿線は人口増加傾向で利用客数も横ばいでほとんど変わっていないのである。
昼間だけに限れば自由席を1両減車し自由席3両と1号車の4両編成とすることができるが、平日夕方はそれでは輸送力が足りず現状通り自由席が4両必要なほか、平日朝も従来通り2両増車して自由席6両で運転する必要がある。つまり快速マリンライナー減車ができなそうだ。
とはいえJR西日本もJR四国も合理化の一貫して普通列車の削減も行っているし、JR西日本では新快速の運転区間短縮を積極的に行っている。そう考えると瀬戸大橋線快速マリンライナーの減便もなくはなさそうではあるが、東京~高松間で航空機と競合していることもあり昼間の30分間隔運転は、深夜の1本の減便を除いて運転本数をかたくなに維持している。
とはいえ航空機との競合は新幹線拠点駅間で3時間以内で移動できれば航空機から客を奪えるので、速達性が重要なのは新幹線で合って実は岡山~高松間の所要時間短縮はさほど大事ではない。実際東京~高松間の利用者が増えたのは東海道山陽新幹線の最速達列車「のぞみ」を増やしたからであってマリンライナーの効果は小さい。
そう考えると普通列車の運転本数を減らすことが目的であるならば、昼間に限り快速マリンライナーのうち毎時1本を大元と備前西市停車とすることで快速列車毎時1本削減、茶屋町~児島間停車とすることで茶屋町~児島間の普通列車毎時1本削減、朝夕に端岡停車とすることで予讃線快速サンポートを削減などだろう。
ただいずれにしても快速マリンライナーの停車駅拡大に伴う普通列車の減便なので、快速マリンライナーの自由席4両は維持するだろう。
6. 新車更新で快速マリンライナー全車JR西日本車両に回帰か
そもそもJR会社間をまたぐ列車は列車調整キロで調整し車両使用料が発生しないようにしている。これは国鉄分割民営化時の1987年4月1日時点では多数のJR会社またぎ列車があったが、取り決めとして列車走行キロで調整することで増車しても追加の調整を必要としないようにするための措置でもある。
1988年4月10日の瀬戸大橋線開業によりJR西日本とJR四国で相互直通運転がスタート、JR他社への乗り入れと同様列車走行キロで調整することとした。JR四国車は岡山まで特急型車両を乗り入れ、JR西日本車両は快速マリンライナーと岡山~琴平・観音寺間の普通列車を担当し、列車走行キロで調整することで車両使用料を発生させないでいた。
ただ、国鉄分割民営化の当初の想定よりJR東日本・JR東海・JR西日本の業績が良かった一方で、当初の見込み通りJR四国は経営難に陥っていた。このため快速マリンライナー用車両をJR西日本車のみの213系からJR四国車5000系とJR西日本車223系の連結編成とすることで快速マリンライナー内だけで車両使用料調整を完結、残るJR四国車による岡山乗り入れ分はJR西日本乗り入れ区間岡山~児島間においてJR西日本がJR四国に車両使用料を支払うことでJR四国の収入を少しでも増やそうとしたのである。
また一説には在来線では料金収入はその車両を保有している車両が総取りするともいわれている。1988年の瀬戸大橋開通に伴う快速マリンライナー運行開始当初は全車JR西日本車だったためグリーン料金。指定席料金もJR西日本の収入となっていたが、2003年の車両更新によりグリーン車と普通車指定席がJR四国5000系に移ったためグリーン料金と指定席料金収入がJR四国に料金収入が入るようになっているようだ。
ただ2020年、全世界的に旅行利用が大きく減ったことからJR西日本の経営が大きく傾き、2021年から各種お得なきっぷの値上げを図り始め山陽新幹線「のぞみ」「みずほ」の値上げ、割安なB特急料金の廃止、鉄道駅バリアフリー料金制度による大阪近郊の10円値上げや特定運賃区間の一部値上げなどを図らざるを得なくなってきた。もはやJR西日本に財務的余裕はない。
一方のJR四国でも全線の運賃値上げを図ったものの、2019年より国が方針変更、財務状況がどうしようもなくなった際にはJR北海道同様沿線の県や日本国が補助金を出してくれる状況にある。
はて、余裕がなくなったJR西日本は今後も日本国の後ろ盾があるJR四国の財務支援として車両使用料を支払う必要はあるのだろうか。いやない。ないとなれば瀬戸大橋線快速マリンライナーの車両更新で全車JR西日本車の編成に戻しJR西日本が増収を図るのではないだろうか。
2024年時点で瀬戸大橋線快速マリンライナーは原則5両編成での運転となっている。が、JR四国5000系とJR西日本223系を連結している関係で車内トイレを1号車と4号車の2か所に設置しなければならなくなっている。もし全車JR西日本車として5両固定編成とすることができれば、車内トイレを1号車のみに集約することができトイレ清掃費用を抑えることができる。この点でも合理化を図ることはできるだろう。
(2024.07.16.追記)2024年7月16日、JR西日本とJR四国は瀬戸大橋線快速マリンライナーについて車両置き換えなしで指定席およびグリーン料金を2024年10月1日より値上げすると公表した。
指定席料金は330円~530円から通年840円に、グリーン料金は50km以内780円から1,010円に、50km超1,000円から1,260円に値上げすることとなった。グリーン料金はJR東日本普通列車グリーン車の紙の券発売価格と同額となっている。
ただネット予約e5489のチケットレス特急券利用の場合、指定席料金は330円から530円へ200円の値上げで済むほか、グリーン料金は780円と1,000円で据え置くこととなった。チケットレス料金券として発券すればほぼ値段据え置きであることを踏まえると、何も知らない遠距離客を狙い撃ちに値上げしているようだ。
7. 結び
今回の瀬戸大橋線快速マリンライナーの車両置き換えでは、建前上バリアフリー化と空気抵抗の削減を図る一方で、全車JR西日本車に戻すことで料金収入をJR西日本の手取りとするほか、座席の質を上げることで値上げする可能性が高い。
今後JR西日本岡山支社・広島支社でどのようなダイヤ改正を実施するのか、見守ってゆきたい。
関連資料 – 第37回定時株主総会ご招集通知 – JR西日本
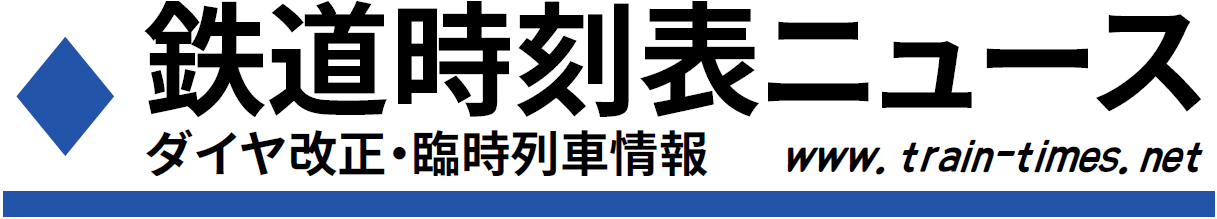








コメント